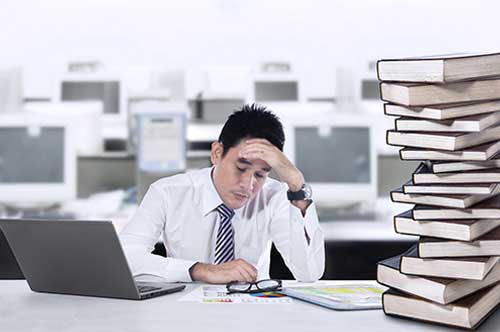事務・管理の残業代

こんな職業の方が対象です
一般事務、データ入力・OAオペレーター、営業事務、労務・人事事務、経理・会計事務、総務事務、秘書、貿易事務、医療事務、介護事務、調剤薬局事務、法律事務(パラリーガル)、受付、コールセンタースタッフ、工場事務、在庫管理・商品管理業務など
1、こんな場合は残業代を取り戻せる?弁護士が判定!
事務職であっても残業代の支払いは必要
1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて労働をした場合には残業代が発生します。「事務職だから残業代はでない」というのは、会社の勝手な言い分で、違法です。今すぐ弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

労働時間に含まれるため残業代請求は可能
労働時間とは、使用者(雇用主)の管理監督下におかれている時間をいいます。掃除や片づけのための早朝出勤が義務付けられている場合には、労働時間に含まれる可能性が高いでしょう。

予想以上に取り戻せるケースもある
残業代は、過去に遡って請求することができます。遡れる期間は、残業代が発生してから2年(2020年4月1日以降に支払われる賃金については3年)です。1か月の残業代が少なくても、数年分をまとめて請求すると、予想以上の残業代になるケースもあります。 かかる費用も含めて判断いただく必要があるため、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

1人で悩むより、弁護士に相談を
無料
今すぐ簡単チェック!
2、事務・管理の残業時間が長い理由
(1)細かな業務・雑務の積み重ねで、残業になっている
事務員といえば残業が少なく、ホワイトな職種だと考えられがちですが、実は多くの事務員が毎月長時間とはいえないながらも、一定時間の残業を行っています。
事務員は他の職種と比較すると、サービス残業を強いられることが少ないイメージですが、「始業前・終業後の清掃や雑務」、「昼休憩中の電話対応」、「他の従業員の手伝い」などは、「労働時間に入らない」として、給与が支払われていないという方も多いのではないでしょうか。
特に中小企業では事務員が非常に少なく、さまざまな雑務を任せられるケースも少なくありません。日用品や事務用品の買い物、書類の発送から経理処理まで、「何でも屋状態」になっている方も多いでしょう。
ですが、そういった働き方の場合は、細かい業務が積み重なった結果、業務量が多く長時間の残業になってしまいがちです。
(2)世相や繁忙期などの影響で、長時間残業をせざるを得ない
事務員は会社の繁忙期や大量受発注、世相の変化などに応じて、業務量が大幅に増減します。
たとえば、最近では新型コロナウイルスの影響により、医療関連・製薬関連などの業界で事務・管理の業務に従事している方は、業務量が増え長時間労働を余儀なくされているでしょう。
また在宅需要が増え、通販事業・宅配サービス事業などの業種で事務・管理の仕事を行っている方なども、業務量が多くなり、負担が大きくなっていることが推察されます。
他にも人事や採用といった職種では就職活動シーズンや、新入社員が入社する年度始めが多忙になりがちですし、製造業や商社で、工場事務、営業事務に従事している方は、客先の都合や季節・顧客の増加によって受発注が増えれば業務が増えます。
事務職は「ホワイトで残業時間が少ない」というイメージですが、こういった世相・繁忙期・客先の都合などの影響を受け、長時間労働をしないと業務が回らず残業が多くなるケースがあります。
(3)年単位で考えると、相当な残業時間になっているケースも
「毎月の残業時間はそこまで多くないし、請求してもたいした残業代を取り戻すことはできないのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、年単位で残業時間を計算した場合はどうでしょうか。
月の残業時間自体は少なくても、年単位で積み重なった結果、ふたを開けてみると、予想以上の残業代請求できる、というケースもあります。
特に勤務年数が長い方は、気づかないうちに相当な残業時間になっている可能性があります。
1人で悩むより、弁護士に相談を
無料
今すぐ簡単チェック!
3、事務・管理で残業代が支払われていない方は、弁護士に相談を
(1)残業代請求には証拠が必要。こんなものが証拠になる
長時間の残業を強いられているのに、残業代が未払いとなっている場合は会社に請求しましょう。
労働時間を示す証拠があれば、請求できる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
事務職であれば、タイムカードや入退室記録が破棄されていても、パソコンのオン・オフのログや、業務に関連する資料のデータ入力をした日時なども証拠となり得ます。
ご自身で集められそうな証拠は、そろえておくと良いでしょう。
(2)証拠がなくても、「まずは弁護士に相談」でOK
もちろん、「手元に証拠がない」という場合でも弁護士に相談して構いません。
弁護士は、証拠の集め方からアドバイスをしてくれます。
また、ご本人で証拠を集めることが難しい場合は、弁護士が会社に対して勤務記録の情報開示を求めることにより、証拠を集めることもできます。
ベリーベスト法律事務所は、残業代請求のご相談に関しては何度でも無料です。
「自分の残業代はいくら?」と気になったら、お気軽にご相談ください。
1人で悩むより、弁護士に相談を
無料
今すぐ簡単チェック!
4、関連コラム・関連コンテンツ
関連コラム
事務・管理で働く方に多いお悩みについて、弁護士がコラムで解説!
あなたの悩みが解決できるかもしれません。ぜひご覧ください。
-
2021年02月18日
- 残業代請求
- 残業代
- 30時間
- 労働基準法
- 弁護士
 月30時間の残業代はどのくらい?支払われていなかった場合の対応
月30時間の残業代はどのくらい?支払われていなかった場合の対応あなたの残業代は正確に支払われているでしょうか?
「毎月の残業は30時間程度だが、給与明細を見ても少ないように感じる……」と疑問を感じながらも、どうしたらよいか分からず、うやむやにしていませんか?残業については、労働基準法で規定されています。平成31年4月から働き方改革関連法が施行され、長時間残業が厳しく規制されるようになりました。
月30時間の残業は、後述する36協定を適切に締結している限り、労働基準法には抵触しませんが、未払いの場合はもちろん違法です。
この記事では、残業に関する法律の基礎知識から残業代の計算方法、残業代の請求方法について解説します。
コラム全文はこちら -
2020年11月05日
- 残業代請求
- 残業代
- 時効
- 弁護士
 未払い残業代の請求の時効が3年間に延長。残業代の計算と請求方法は?
未払い残業代の請求の時効が3年間に延長。残業代の計算と請求方法は?2020年4月から民法改正の影響を受けて労働基準法の内容も見直され、未払い残業代の消滅時効期間が2年から3年に延長されることになりました。企業で働いている方にとって、自分にも未払い残業代が発生しているのか、その際には請求できるのかと気になるのではないでしょうか。
この記事では、未払い残業代の時効延長に関する基本事項に加えて、残業代の計算方法や請求方法を弁護士がわかりやすく解説します。未払い残業代が発生している可能性がある方は、ぜひご一読ください。
コラム全文はこちら -
2019年10月16日
- 残業代請求
- 平均
- 残業時間
- 働き方改革
 サラリーマンの平均残業時間は?未払い残業代請求の可否やポイントは?
サラリーマンの平均残業時間は?未払い残業代請求の可否やポイントは?サービス残業が当然のように行われていた時代から、平成27年に電通の女性新入社員が過労自殺した問題もあり、長時間労働への風当たりは年々強さを増しています。働き方改革関連法が平成31年4月から順次施行されるなど、法的な手当てもなされるに至っています。こうした流れを受け、企業・労働者双方の労働時間に対する意識が変わり、サラリーマンの残業時間は年々減少傾向にあります。
その一方で、業務量自体は変わらないことから、持ち帰りの仕事を行わざるを得ないなど、残業代が支払われない、サービス残業をしている人もいると思われます。こんなに働いているのに実労働時間に見合った給料をもらえていない、と不満を抱える方は少なくないでしょう。
今回は、日本のサラリーマンの平均残業時間を把握した上で、残業代を請求できる労働及び残業時間の上限規制について解説し、未払いの残業代を請求する際のポイントについてもお伝えいたします。
コラム全文はこちら -
2019年11月08日
- 残業代請求
- いくら
- 計算方法
- 請求方法
 残業代はいくら支払われている?適切な計算方法と未払い分の請求方法を解説
残業代はいくら支払われている?適切な計算方法と未払い分の請求方法を解説会社勤めをしていると、業種や職種によっては時間外の業務が発生することも珍しくありませんが、原則として、所定時間外の労働に対しては残業代が支払われる必要があります。
しかし、実際の勤務時間に対して残業代の支給額が少ないと感じる方もいるかもしれません。そのような場合は、適正な計算方法で残業代が算出されていない可能性があります。
残業代には、労働時間や勤務日数などの一定条件を満たすと賃金が割増しされる仕組みがあります。もしもご自身の残業代が適正に支給されていない疑いがある場合は、正しい方法で計算されているか確認しましょう。
今回の記事では、残業代の相場や計算方法について解説します。
コラム全文はこちら -
2019年09月18日
- 残業代請求
- サービス残業
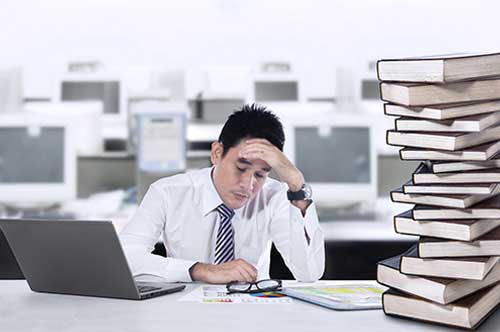 サービス残業は当たり前ではない!違法行為になる理由を徹底解説!
サービス残業は当たり前ではない!違法行為になる理由を徹底解説!毎日サービス残業をしていると、次第に「これは当たり前のことなのか?」「疑問に感じる自分がおかしいのか?」などと、感覚が麻痺してくることがあるでしょう。周囲に聞いても「自分も同じだよ」などといわれてしまい、皆がそうなのだから我慢するしかないと感じるかもしれません。
しかし、サービス残業は本当に当たり前のことなのでしょうか。サービス残業をさせている企業に違法性はないのでしょうか。
今回は、サービス残業を強いられている労働者の方に向けて、サービス残業の法律的な取り扱いや対処法について解説します。
コラム全文はこちら
関連コンテンツ
事務・管理に多い働き方の、残業代請求のポイントを弁護士が解説しています。