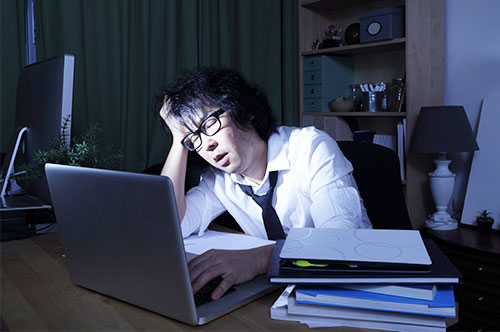化学・バイオ業界の残業代

こんな職業の方が対象です
バイオ技術者、製薬会社・医薬品製造、環境分析技術者、エネルギー系研究・技術者、化学系研究・技術者、環境計量士、作業環境測定士、海洋工学系研究・技術者、食品技術開発研究者、農林技術研究者、畜産技術研究者、バイオベンチャーなど
1、こんな場合は残業代を取り戻せる?弁護士が判定!
裁量労働制であっても残業代は支払われる場合がある
裁量労働制では、実際に働いた時間ではなく、事前に決めたみなし労働時間が労働時間となります。そのため、みなし労働時間を1日8時間超と設定した場合には、8時間を超える部分について残業代が発生します。

原則として、裁量労働制で働く労働者に対して残業を命じることはできない
裁量労働制では、業務遂行の手段や時間配分について労働者の裁量に委ねられています。 そのため、使用者(雇用主)が労働者に残業を命じることは、原則として違法です。ただし実際の状況を踏まえた上で、適切に判断する必要がありますので、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

自主的な勉強時間は労働時間には含まれない
終業後に自主的に勉強をすることは、使用者(雇用主)によって義務付けられたものではありませんので、労働時間には含まれません。ただし、「自主的な勉強」としつつ「実質的には会社の命令で勉強していた」というケースであれば、指揮命令下におかれていたことになり、残業代が請求できるケースもあります。

深夜残業代が支払われていなければ請求できる
午後10時から午前5時までに行う労働については、深夜労働による割増賃金を支払わなければなりません。1日8時間以上労働しているのに、さらに同じ日に深夜労働もしているという場合は、通常賃金+割増賃金を請求することができます。

1人で悩むより、弁護士に相談を
無料
今すぐ簡単チェック!
2、化学・バイオ業界の研究職の残業時間の問題点
(1)化学・バイオ業界で研究職に就いている方の残業時間は平均より長い傾向が
化学・バイオ業界で研究職として働いている方、たとえば製薬会社の研究職や化学製品開発スタッフ、バイオ研究員、データサイエンティストなどといった職種の方の残業時間はゼロではありません。
厚生労働省の毎月勤労統計調査(令和3年2月確報)によると、学術研究等の産業に従事している方の所定外労働時間は13.9時間。全産業の合計が9.3時間ですので平均を4時間以上、上回っています。
短い時間だと思われるかもしれませんが、年単位で見れば約167時間となります。
(2)研究職には残業代を支給しないとしている企業もある
本来であれば、一部の例外を除き、残業代はすべて支払われるべきと労働基準法で定められています。
しかしながら、管理監督者である場合や、高度プロフェッショナル制度、裁量労働制を採用している場合には、残業をしても残業代を支払う必要があるとも限りません。
この仕組みを利用して、研究職にはこれらの制度を導入し残業代を支給していない企業も存在します。
ところがこれらの例外を適用するためにはさまざまな条件をクリアしなければなりません。「管理監督者だから」「高度プロフェッショナル制度だから」「裁量労働制だから」と残業代を支払っていない場合でも、実は制度が適法に運用されていないなどの理由で、残業代の支払い対象である可能性もあるのです。
また、「従業員が自主的に残業をしていたから」と残業代の支払いを拒む企業も存在します。
1人で悩むより、弁護士に相談を
無料
今すぐ簡単チェック!
3、化学・バイオ業界で働いていて、残業代に悩んだら弁護士へ
化学・バイオ業界で働いていて、長時間労働しているのに残業代が支払われないことに疑問・不安を感じている場合は、まずは弁護士に相談してみましょう。
前述した、「管理監督者」「高度プロフェッショナル制度」「裁量労働制」といった理由により残業代の支払いを受けていない方は、弁護士に相談することで、過去の未払い残業代を請求できる可能性があります。
それ以外の方でも、そもそも会社の残業代の支払い方法が法的な基準を満たしておらず、残業代が適切に支払われていない場合もあります。
自主的な残業(会社の指揮・監督下にない残業)の場合には、残業代は支給されませんが、表向きは「自主的な残業」という形でも、実質的には残業しないと業務が回らず、残業を余儀なくされていたようなケースでは、「黙示の残業命令」があったものとして、残業代の支払いが認められるケースもあります。
自分は残業代を請求できるのか分からない、手元に証拠がない、といった場合でも、「まずは法律に詳しい専門家に相談してみる」ことが大切です。
1人で悩むより、弁護士に相談を
無料
今すぐ簡単チェック!
4、関連コラム・関連コンテンツ
関連コラム
化学・バイオ業界で働く方に多いお悩みについて、弁護士がコラムで解説!
あなたの悩みが解決できるかもしれません。ぜひご覧ください。
-
2020年07月08日
- 残業代請求
- 裁量労働制
- 悪用
- 未払い賃金
- 残業
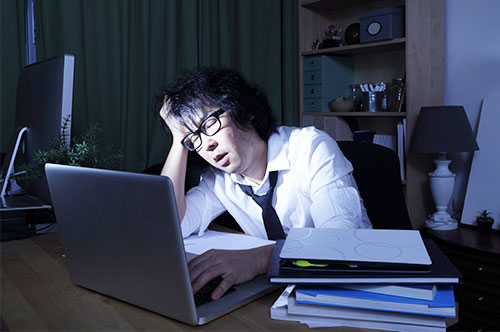 裁量労働制だから残業代は支払わない、と言われたら。会社に制度を悪用された場合の対処法
裁量労働制だから残業代は支払わない、と言われたら。会社に制度を悪用された場合の対処法令和元年10月、有名なアニメ映画などを手掛けてきたアニメ制作会社の社員が「裁量労働制が違法に適用され、残業代が支払われなかった」として会社を提訴しました。
確かに効率的で自由な働き方が求められる現代において、裁量労働制は時代の流れを反映した制度として注目されています。
しかし、会社側が制度を悪用するケースもあり、残業代を支払わないことの根拠としている事例も目立つようになりました。多くの労働者が「裁量労働制だから」と本来もらえるはずの残業代が支払われず、未払い賃金が発生する事態も確認されています。
本コラムでは「裁量労働制」をテーマに、制度の詳しい内容をチェックしながら、裁量労働制が悪用されて未払い賃金が発生している場合の対処法について弁護士が解説します。
コラム全文はこちら -
2018年10月03日
- 残業代請求
- 裁量労働制
 大手電機会社の過労死問題から考える、裁量労働制でも残業代請求できるケースとは?
大手電機会社の過労死問題から考える、裁量労働制でも残業代請求できるケースとは?「裁量労働制が適用される場合、残業代請求できない」と考えていませんか?
「裁量労働制」を適用できるケースは非常に限定されており、会社から「裁量労働制」と言われていても、残業代請求できる可能性があります。今回は、会社から裁量労働制だから残業代は出ないと言われていても残業代請求できる可能性があるケースについて、弁護士が詳しく解説します。
コラム全文はこちら -
2020年06月08日
- 残業代請求
- 40時間
- 残業代
- 計算方法
- 請求方法
 週40時間以上の労働に残業代はでるの?未払い分の請求方法と対策
週40時間以上の労働に残業代はでるの?未払い分の請求方法と対策働き方改革が進められるなかで、「労働時間とは」「時間外労働とは」という知識が啓発される機会が増えています。
厚生労働省は、平成31年から令和2年にかけて段階的に施行される時間外労働の上限規制について「時間外労働の上限規制|わかりやすい解説」と題したリーフレットを公表しており、労働時間の限度として「1週40時間」が紹介されています。
1週間につき40時間とは、労働基準法 第32条1項において規定されている労働時間です。定められた労働時間を超えると、時間外労働として残業代の支払い対象となります。ただし、場合によっては残業代が発生しないこともあるので、正しい知識を身につけておきましょう。
本コラムでは「週40時間以上の労働に残業代はでるのか」をテーマに、残業代がでるケースとでないケース、残業代の計算方法、未払い残業代の請求方法などについて弁護士が解説します。
コラム全文はこちら -
2020年08月25日
- 残業代請求
- 長時間
- 残業
- 辛い
- 対処法
- 弁護士
 残業で辛いときの対処法は? 法律で定められている残業時間の限度を解説
残業で辛いときの対処法は? 法律で定められている残業時間の限度を解説長時間の残業が毎日続き、心身ともに辛い状況にある……。会社勤めをしてこのような悩みを抱えている方は少なくないでしょう。長時間労働は身体に疲労を蓄積させるだけでなく、心にもダメージを負わせてしまうリスクがあるため、早急に対処するべき問題です。
しかし、毎日の仕事に追われて具体的な対策を立てられず、あるいは転職しようにも上司から強い引き留めにあっており困っているという方もいるでしょう。
この記事では、残業が辛いときにすぐに取り組める身近な工夫から、法的な対処法までを解説します。基本的な知識として、法律における残業の限度時間についても知っておきましょう。
コラム全文はこちら -
2020年09月08日
- 残業代請求
- 深夜
- 残業
- 計算方法
 深夜まで残業しているのに、残業代が貰えない方へ。正しい深夜残業代の計算方法
深夜まで残業しているのに、残業代が貰えない方へ。正しい深夜残業代の計算方法業界や職種によって、また、繁忙期など時期によって、深夜までの残業をしなければならないことも珍しくありません。しかし、深夜まで残業したにもかかわらず、適切な残業代が支払われないという悩みを持った方もいらっしゃるでしょう。
もしも、あなたが適切な残業代の支払いがされていないと少しでも気になっているのであれば、残業代を請求することを考えた方がよいかもしれません。
今回は、深夜残業における残業代の計算方法や深夜残業代に関して知っておくべきポイント、労働時間該当性の判断基準、時効などについて解説をします。
コラム全文はこちら
関連コンテンツ
化学・バイオ業界に多い働き方の、残業代請求のポイントを弁護士が解説しています。