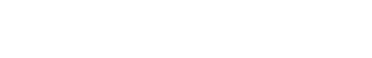法人のお客様 Corporate
通達を否定した裁判例
Cases Whereby Tax Rulings Were Disaffirmed国税庁の発する通達には各種のものがありますが、そのうち法令解釈通達と呼ばれるものは、法令の公的解釈を示すという点で重要な意義を有するものであり、課税実務において大きな影響力を持っています。
そのため、納税者としても、課税当局から、「通達にはこう書いてある」と言われると、それに従わなければならないと考えがちです。
しかしながら、国税庁の通達は、その下にある機関(国税局や税務署など)に対しては拘束力を持っていますが、国民を直接拘束するものではありません。実際に、裁判所が通達による法令の解釈を否定し、通達に基づく課税処分を取り消す例があります。
外れ馬券事件

これは新聞報道でも有名な事件であり、争点は「外れ馬券も必要経費として所得から控除することができるか」という点にあります。
実は、個人の所得は税務上10種類に分類され、それぞれの所得に応じて、税率や損益通算(収益を損失で相殺して、所得金額を下げること)ができるかどうかのルールが違います。
そして、一般に、ギャンブルで得た収入は「一時所得」に該当するとされ、「その収入を生じた行為をするため……直接要した金額」のみを経費として収入から控除できますので、通常、馬券が当たった場合に損失にできるのは当たり馬券の代金のみです(なお、一時所得は50万円までは課税されませんので、趣味の範囲で競馬を楽しむ人は当たり馬券による収入を申告することはないと思います)。
ところが、本件は、納税者が、インターネットを通じた馬券購入と競馬予想のソフトウェアを組み合わせ、機械的に反復継続して大量の馬券を購入し、多額の払戻金を得て利益を得ていたという事案です(訴訟の対象となったものだけでも、3年間で約28.7億円の馬券を購入し、約30.1億円の払戻金を得ていたということです)。
ここまで来ると事業の一種のようにも見えます。そこで、納税者は、本件の払戻金は雑所得に該当するとして、外れ馬券の代金も経費計上して税務申告を行ったため、課税当局は、「競馬の馬券の払戻金」は一時所得に該当すると定めた通達(所得税基本通達34-1(2))に基づき、外れ馬券の代金を控除しない所得を基準とする課税処分を行うとともに、納税者が虚偽の確定申告をしたとして所得税法違反で刑事告訴しました。
納税者は、課税処分の取消しと無罪を求めて争いました。税務訴訟よりも刑事訴訟での審理が先行し、大阪地裁(第一審)では納税者が敗訴しましたが、大阪高裁(控訴審)及び最高裁(上告審)では納税者が勝訴しました。
最高裁の結論
「被告人が馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの本件事実関係の下では、払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとした原判断は正当である」

この刑事裁判の結果を受けて、課税当局が自ら課税処分を取り消したため、本来の税務訴訟の方も終了しました。
また、上記最高裁判決が言い渡された後、国税庁も上記通達に「馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する」という注記を加えました。
株式保有特定会社事件

下級審裁判例ではありますが、通達と異なる判断をした東京高裁(控訴審)における納税者勝訴判決が確定した事件を紹介します。
この事件の事案は、ある非上場会社(仮に「A社」とします)の主要株主である経営者及びその親族が、その経営者の母親の死亡により相続した株式(A社が発行したもの)について、相続税の申告をしたところ、課税当局が、納税者はその株式の評価を誤っており、相続税が過少に申告されているとして更正処分を行ったというものであり、非上場会社の株式を相続税の算定上どのように評価するべきかが問題となりました。
この点について、相続税申告において強い影響力を持つ通達「財産評価」(実務上「財産評価通達」といわれており、以下ではこの呼称を使用します)189(2) には、事件当時、評価対象となる株式の発行会社が所有する資産のうち、株式の価額の合計額の占める割合(株式保有割合)が25%以上となる会社(A社は、株式保有割合が25.9%でした)は、「株式保有特定会社」であるとして、純資産価額方式で評価を算定することとが定められていました(ちなみに、相続税法22条では、簡潔に「相続……により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による」と定められています)。
純資産価額方式による株式評価は、通常であればA社に適用されるべき原則的評価方法である類似業種比準方式に比べて、株価が高く評価される傾向にあります。
財産評価通達において、株式保有特定会社についてのみ、純資産価額方式による株式評価をするべきであると定められたのは平成2年からです。その理由は、会社の資産構成が株式に偏っている株式保有特定会社については、その会社(今回のケースでいえばA社)の発行株式の価値が保有している株式(今回のケースでいえば、A社が保有している他社発行株式)の価値に依存する割合が高いのですが、平成2年より前において、こうした会社の株式も類似業種比準方式によって低額に評価されることを利用した租税回避行為が横行したことから、それを防止するためでした。
このように、財産評価通達189(2)は、平成2年当時は合理性があるものでしたが、本件の納税者は、その後の持株会社の解禁(平成9年独占禁止法改正)等によって状況が変化したとして、「株式保有割合が25%以上の会社を株式保有特定会社として純資産価額方式による株式評価を強制することは、実態にそぐわない」と争いました。
裁判所も、株式保有割合25%という「判定基準が本件相続開始時である平成16年においても合理性を有しているというためには、この時点においても株式保有割合25%以上であることをもって当該会社の資産構成が著しく株式に偏っていると評価できなければならない」とした上で、「本件相続開始時においては、株式保有割合25%という数値は、もはや資産構成が著しく株式に偏っているとまでは評価できなくなっていたといわざるを得ない」と述べて財産評価通達189(2)の合理性を否定し、納税者の言い分を認めました。
課税当局は、この判決に対して上告することを諦め、財産評価通達189(2)を改正して、株式保有割合が50%以上の会社でなければ株式保有特定会社にならないと定めました。