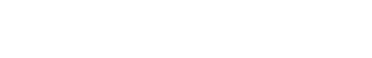- ベリーベスト法律事務所
- 法人のお客様
- 税務訴訟(審査請求・税務調査・訴訟対応)
- 税務訴訟(審査請求・税務調査・訴訟対応)とは
- 高レベルな論点の裁判例
法人のお客様 Corporate
高レベルな論点の裁判例
Cases Whereby Complex Tax Issues Were Litigated国税庁の発する通達には各種のものがありますが、そのうち法令解釈通達と呼ばれるものは、法令の公的解釈を示すという点で重要な意義を有するものであり、課税実務において大きな影響力を持っています。
そのため、納税者としても、課税当局から、「通達にはこう書いてある」と言われると、それに従わなければならないと考えがちです。
しかしながら、国税庁の通達は、その下にある機関(国税局や税務署など)に対しては拘束力を持っていますが、国民を直接拘束するものではありません。実際に、裁判所が通達による法令の解釈を否定し、通達に基づく課税処分を取り消す例があります。
ここでは、代表的なものを二つ取り上げます。
ガーンジー島事件

タックスヘイブン対策税制との関係で、最高裁が非常に重要な判示を行ったのが、ガーンジー島事件です。
タックスヘイブン対策税制というのは、簡単にいえば、日本国内の納税者(個人又は会社)が税率の低い外国・地域(タックスヘイブン)に会社(国内の会社が設立した場合は、外国子会社ということになります)を設立した場合に、外国会社の所得を国内の納税者の所得と合算して課税するというものです。
これは、もともと日本の納税者が税率の低い国に会社を作って、本来は日本で課税されるべき所得をその会社に貯め込み、課税を回避することを規制しようとするものであり、典型的な規制対象は海外のペーパーカンパニーです(そのため、海外に子会社を設立する経済的合理性があると認められる一定の場合には、適用がありません)。
さて、事案の内容ですが、ガーンジー島というのは、イギリス海峡にあるイギリス王室属領であり、有名なタックスヘイブンです。ここには高度の自治権が認められており、税金についてもイギリス本国と異なる制度が採られています。
この事件の原告は日本の会社であり、ガーンジー島に子会社を設立して税金を納めていましたが、ガーンジー島においては、一定の要件を満たした外国資本法人の所得税(日本でいう法人税)については、税務当局の承認を条件に、0%を超え30%以下の割合の中から税率を選択して申請することができるという制度が採用されており、その子会社は26%の税率を選択して納税をしていました。
なぜ26%にしたかというと、当時の日本では、税率が25%以下の外国・地域について、タックスヘイブン対策税制が適用されていたため、25%やそれより小さい税率を選択すると、タックスヘイブン対策税制が適用され、子会社の所得にも日本の税率が適用されて課税されることになってしまうからです。
これに対し、原告会社を所轄する税務署長は、「そんな制度で納めるお金は税金(法人税法上の「外国法人税」)には当たらないので、本件のガーンジー島子会社にもタックスヘイブン対策税制の適用がある」と主張して、ガーンジー島子会社の所得も合算して原告会社への課税処分を行いました。
この事件において、東京地裁(第一審)及び東京高裁(控訴審)は、税務署長の判断を支持しましたが、最高裁では、納税者である原告会社が全面的に勝訴しました。
最高裁の結論
「本件外国税は、ガーンジーの法令に基づきガーンジーにより本件子会社の所得を課税標準として課された税であり、そもそも租税に当てはまらないものということはできず、また、外国法人税に含まれないものとされている法人税法施行令141条3項1号または2号に規定する税にも、これらに類する税にも当たらず、法人税に相当する税ではないということも困難であるから、外国法人税に該当することを否定することはできない」

その後の税制改正により、ガーンジー島の上記法人所得税制度を利用した節税法は封じられることになりましたが、当時の最高裁の判断は、「租税法律主義」に基づき法令で定められた課税要件を重視したものであり、法的安定性及び納税者の予測可能性を保護した妥当なものであったと評価されています。
ヤフー事件

「巨額な課税処分についての裁判例」のIBM事件も、行為計算否認規定の適用が問題となった事件ですが、これとほぼ同時並行のようにして第一審から上告審まで判決が言い渡されてきた事件に、ヤフー事件があります。
この事件は、ヤフーがグループ会社を買収した上で合併し、当該グループ会社の繰越欠損金が合併後のヤフーに引き継がれることを前提として税務申告をしたところ、税務当局が、当該合併による繰越欠損金の引継ぎを否認し、約180億円の法人税を追徴する課税処分を行ったという事案に関するものですが、IBM事件と同様に、組織再編行為の否認が論点となりました(厳密には、適用される法人税法の条文が異なります)。
ところが、ヤフー事件では、結論として、納税者であるヤフーが敗訴しています。
最高裁では、法人の行為を否認するべきかどうかについて、下記のような理由で、ヤフーの行った組織再編行為は否認されるべきであると判示しました。
最高裁の結論
- 当該法人の行為又は計算が、通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか
- 税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか
等の事情を考慮した上で、当該行為または計算が、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨および目的から逸脱する態様でその適用を受けるものまたは免れるものと認められるか否かという観点から判断」

もちろん、事案が異なるために単純な比較はできませんが、IBM事件と比較すると、ヤフー事件においては、税務調査段階において弁護士の関与がなく、かなり深い調査がなされており、ヤフーにとって不利な証拠が訴訟の場に数多く提出されたことも一因といわれています。
デラウェア州LPS事件

事業体に関する課税が問題となった事案として有名なのが、アメリカデラウェア州のリミテッド・パートナーシップ(LPS)を使った節税法(海外不動産を購入した際の減価償却費を損金算入して、日本で得た個人所得と相殺するという手法)に関する複数の訴訟であり、一時期、各地の裁判所で判決が出されていて注目を集めました。
要するにLPSが法人として扱われるかどうかが問題となったものですが、法人扱いされれば、LPSにおける事業による収益の配当が分離課税の対象となる配当所得となり、そうでなければLPSによる収益は他の所得と損益通算が可能な不動産所得などに該当するということで、法人扱いしたくない納税者と法人扱いしたい課税当局の判断が分かれました。
LPSへの課税については、「チェック・ザ・ボックス・ルール」が採用されているのが特徴です。これは、届出書の四角い欄にチェックを入れることで、事業体課税か構成員課税かを選べるというものです。課税を選択できるという意味では、ガーンジー島事件とも共通する点があり、この種の融通無碍な制度は日本にはありませんので、できるだけ課税したい課税当局とできるだけ課税を逃れたい納税者とで、見解の相違が生じてしまうわけです。
特に利用されたのが、事業体関係の規制が緩やかなデラウェア州のLPSであり、訴訟では、東京高裁および大阪高裁では納税者が負け、名古屋高裁だけ納税者勝訴の判決が出ました。このように、LPS訴訟は、高裁段階でも判断が真逆に分かれてしまうようなレベルの高い論点に関する訴訟であるといえると思います。
これらの事件が上告され、うち一つの事件に関し、最高裁は、下記のように判示し、課税当局を勝たせ、納税者を敗訴させました。以後、デラウェア州LPSに関しては、判断が統一されることとなりました。
最高裁の結論
「本件各LPSは、・・・権利義務の帰属主体であると認められるのであるから、所得税法2条1項7号等に定める外国法人に該当するものというべきである」

この判決に対しては、デラウェア州LPSが、選択的とはいえ構成員課税であることが基本的属性であり、日本法における法人(法人という事業体自身が課税対象となっています)に相当するものではないはずであるという有力な批判があります。